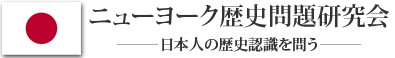歴史力を磨く 第23回
NY歴史問題研究会会長 髙崎 康裕
■ 平成最後の夏に ■
靖国神社は来年創建150年を迎える。では、この靖国神社はどのようにして誕生したのであろうか。それは明治維新の際の、官軍東征軍の陣中慰霊祭から始まった。慶応4年の4月末(明治と改元されたのはこの年の9月)に、維新に際しての戦火に斃れた者の霊を慰めるために戦没者将兵の招魂慰霊祭を挙行するという文書が出され、翌明治2(1869)年6月に最初の招魂祭が行われた。当初この祭祀施設は東京招魂社と呼ばれたが、明治12年に改称されて、靖国神社と呼ばれるようになった。
一方、靖国創建から間もない明治10年には西南戦争があり、その後も日清戦争、北清事変、日露戦争と外国との戦いが続いた。それに合わせて、日清戦争以降は対外戦争で斃れた英霊を如何に祀るかという問題に当時の日本人は直面していくことになった。その時に靖国神社という「国の為に命を捧げた人達の霊をお祀りする」施設があったということが、極めて大きな意味を持ったのである。出征する兵士たちは、「自分たちがたとえ戦死してもあのお社に祀っていただける。あの社は天皇陛下も御親拝になる極めて尊いお社である。微々たる存在にすぎない自分が国の為に命を捨てて戦ったということで、天皇陛下までお参りに来て下さる」と理解をし、それが非常な励みとなった。
それが今日では、靖国神社は軍国主義のために創られ、利用されたというような批評や報道をよく目にする。しかし国の為に一命を捧げるということが道徳的意味を持つのはどこの国でも価値のある行為であって、決して日本だけの話ではない。言ってみれば、人間にとっての普遍的な道徳の1項目である。そのように、国の為に命を捧げた国民は靖国に顕彰され祀られるということが、西洋列強が日本を圧迫するという非常に厳しい国際環境の中にあっても、日本を近代国民国家たらしめた力の源泉にもなったのである。
その靖国神社の参拝については、中国や韓国からの謂われなき批判や、それに呼応するような国内の参拝反対勢力との対峙を避けようと、首相ですら思うように参拝できない状況が続いている。それは天皇陛下の御親拝についても同じである。そこには、天皇陛下を政治問題に巻き込んではならないという配慮がある。しかし、国家の元首たる天皇陛下自らが靖国に詣でられることこそが、靖国に対する外国や国内の一部の人間たちの迷妄を啓き、国家と民族が蒙っている屈辱を晴らすことに繋がる筈である。
「海ゆかば水漬く屍 山ゆかば草生す屍 大君の辺にこそ死なめ かえり見はせじ」と歌って戦に赴き、散華した兵士たちは互いに靖国での再会を信じていた。その若者たちの憂国の情を汲み、未だ消えぬ無念を晴らすことは、国家の責務でもある。
不遜を承知しながらも、平成最後の夏に、それが実現することを切に願うばかりである。