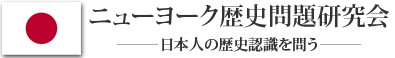歴史力を磨く 第13回
NY歴史問題研究会会長 髙崎 康裕
■ 日本国憲法にみる「主権」とは ■
近代国際法によれば、国家とは領土、国民、主権の3要素を持つものとされる。
16世紀にこの「主権」という言葉が定義づけられて以来、理論上はどんな小さな国家にも「主権」が認められなければならないということが、基本的な理解とされてきた。
その「主権」とは、一言で言えばその国の独立を支えている力、他からの介入に屈しない力である。つまり、「主権」の前提には「力」がある。「力」のないところには、あるいは「力」を封じられているところに「主権」は存在しない。もともと「主権」とは「最高の力」という意味だが、では国家に一切の「力」がないというのは、どのような状態を言うのだろうか。
その例として、国家が戦争に敗れて武装解除をされ、占領下に置かれ、独立を奪われ、一切の政治決定権を奪われた事態が考えられる。そのような状況下では、占領者が全ての政治決定権を握ることから、その国の「主権」が存在する余地はなくなってしまう。
そもそも近代民主主義憲法は、18世紀末のアメリカの独立戦争とフランス革命後に、力と力の争いに勝って「主権」を手に入れた者たちが、それぞれの国で、自らの政治決定権を発揮して制定した憲法に始まる。従って、日本国憲法前文冒頭の「日本国民は…われらとわれらの子孫のために、…ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する」という文言は、近代民主主義憲法という立場からすれば、欠くことのできない一節なのである。
しかし、その文言とは裏腹に、日本国憲法が制定されたとき、主権は日本国民に存してなどいなかった。主権は連合国総司令官に握られており、国会での憲法審議の過程を監視し、許可し、確定したのも最高司令官であった。つまり、日本国憲法には、その最も重要な根底である「主権」の存在という点に於いて虚偽があった。更に、占領当初からの言論統制(プレスコード)によって、新聞、ラジオ等の報道には事前検閲が徹底され、当時の国民にはそのような事情は一切知らされなかった。その結果、国民は連合国総司令部の作成した憲法草案は「日本政府案」だと信じ込まされ、新憲法を祝ったのである。
成文憲法というものは、その国の歴史や伝統、国柄といったものを織り込んで、自主的に作られるべきものであるというのが、世界の憲法学での基本的な考えである。自国に主権がない状態において、占領者が与えた憲法などというものは、近代成文憲法の常識に照らしても、あってはならないものなのである。