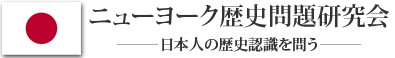歴史力を磨く 第12回
NY歴史問題研究会会長 髙崎 康裕
■ 世界史の中の明治時代 ■
明治時代という約半世紀は、西欧諸国の世界からみれば、自分たちよりもはるかに古い民族統一体としての歴史を有する日本が、どこまで自分たちの文明の尺度に適応していくかを見守っていた歳月でもある。
当時の西欧諸国には、自分たちの文明こそが標準であり普遍であるとの驕慢が染みついていた。彼らは、その自信と圧倒的な軍事力や経済力を背景に、アジアでの植民地政策を推し進めていた。その時代をイギリスの歴史家のトインビーは次のように述べている。「19世紀末の西欧から東方を眺めれば、トルコから清国に至る諸帝国は西欧に抵抗できなかった。インドもベトナムもジャワも、その原住民は羊のように従順に、ただ黙々として毛を刈り取る者に反抗しようとはしなかった。ただ日本だけがきわめて珍しい例外であった」(アーノルド・トインビー『文明の実験』)。
そのような中で、白人西欧列強の植民地政策に対抗して立ち上がった日本には、共に戦い協同する有色国家はなく、世界の中で孤立していた。当然、西欧諸国からは不快感と敵意を浴びせられた。しかし有色人種の誰かが立ち上がらなければ、人種差別は終わらなかった。開国以来の日本の目標は「独立主権の維持」「東亜の安定と世界平和への寄与」「人種平等の確立」という三つに集約できる。特に日露戦争以降、これらの目標は強く日本国民に意識されるようになり、そしてそれらの目標は、結果としてアジア諸国の独立を齎した大東亜戦争にも引き継がれた。
明治の日清、日露の両戦争や韓国併合とその後の統治は、日本にとっては帝国主義時代における国家の生き残りをかけた止むを得ない決断であり、明治政府が進んでそれを望んだわけではない。日本からすれば、当時の清と朝鮮には欧米列強の圧力をはね返す力がないばかりでなく、手をこまねいていれば自らの安全と独立が脅かされるのは間違いない状況の下で、朝鮮半島と支那大陸の安定という難問に踏み込んでいかざるを得ないという事情があった。
そうしてみると、明治という時代は、西欧文明という日本にとっては異質の文明に対して、日本が自己の尊厳を失うことなく、彼らの様式の中でも国家の存在を維持確立していくという、世界史的運命の時代でもあったと言える。そしてそれは日本にとっての栄光の時代であると同時に、決して軽々に忘れることのできない苦難の時代でもあった。
その父祖たちの苦難の記憶を継承し、私たち自身の記憶として遺していくことが、将来の国家像を樹立するためには不可欠の前提であると思うのである。