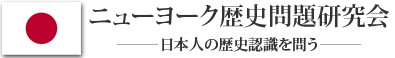歴史力を磨く 第8回
NY歴史問題研究会会長 髙崎 康裕
■ 憲法改正論議を前に:国家の理解 ■
今回の総選挙の結果、改憲勢力が総議員の3分の2を大幅に超えたことから、憲法改正論議の高まりが期待されている。一方、日本のメディアに登場する識者と言われる人たちからは、「憲法は国家権力を縛るもの」という説明がなされ、これが憲法改正はその縛りを解き、「基本的人権の保障」という現行憲法の精神を枉げてしまうのではないかという不安を国民に齎す理由にもなっている。しかしここには「国家」というものについての理解の混乱があると思われる。
先ず、「国家」という場合には意味内容が二つある。一つは「国家があれば憲法がある」という場合の国家だが、これは「共同体としての国家」を指している。これに対して革命によって新たな国家が生まれたという場合の国家は、共同体というよりも「政府」や「統治機構」を指す。英語では政府や統治機構はステイト、国民共同体はネーションと区別されるが、日本ではその区別がされず国家と言っている。つまり、「基本的人権は国家を超えたもの」という場合の国家とは、実は「政府」のことであり、「憲法が出来るためには国家が前提となる」という場合の国家は「国民共同体としての国家」を指す。
日本国憲法の前文にも国家という言葉が出てくる。本来ならばそこでの国家は、二千年以上前から皇室を中心に発展を遂げてきた歴史的伝統的な共同体としての国家が前提となっている筈である。しかし実際の前文は英の思想家ジョン・ロックの「統治論」から引用した、「国政は国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、権力は国民の代表者が行使する」という表現しかなされていない。まるで日本という国が、国民の合意によって作られたような発想に立っている。しかしこれはただの統治機構や政府論にすぎない。
戦後の日本では国家論、共同体としての国家についての議論がまともになされてこなかった。「統治機構としての政府」と「共同体としての国家」が同じ国家という言葉で括られ、国家は権力であり、国家は警戒の対象だと常に批判的に論じられてきた。その結果が、「憲法は国家権力を縛るもの」という理解を生んでいる。
想えば、聖徳太子の十七条の憲法は、国と国民の対立から生まれたのではない。そこに見られるのは和の精神である。日本人にとっての国家は、決して国民と対立関係にあるのではなく、寧ろ国民を包み込んで安全の枠を作ってくれる存在であった。そしてその精神が、「国のかたち」や「国柄」を作ってきた。
この視点こそが、これからの憲法改正論議にも活かされなければならないと思うのである。