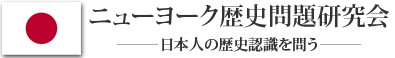歴史力を磨く 第7回
NY歴史問題研究会会長 髙崎 康裕
■ 自らを識るために ■
今年も日米開戦の記憶を辿る日を迎えた。その開戦当時の諸事実については、戦後長く公表されていなかったものも近時明らかにされてきた。例えば開戦直前の日米交渉に於いて米国側にはもはや「交渉」の意図は全くなかったことや、日本海軍による真珠湾の「奇襲」攻撃は単に米大統領の予知するところであったのみか、寧ろ待望するところであったことなどである。しかし実は、当時の米側の意図や、それに追い詰められて行った日本の状況などは、東京裁判でも日本側の弁護人を務めたベン・ブレイクニーやウィリアム・ローガン弁護人の陳述のなかで既に明らかにされていた。
それらの記述によれば、日本はアメリカとの戦争について、開戦の時期、戦線の規模はおろか、そもそも開戦するか否かさえも選ぶことが出来ない状況であった。大本営参謀本部が開戦を決意したのは、米国の対日石油全面禁輸によってであり、米国が禁輸に踏み切ったのは、米国側がほぼ開戦の準備を整え終えてからであった。即ち、開戦の決定を実質的に下したのは、大本営でも天皇陛下でもない。米国政府だったのである。
しかし、敗戦後の「あの戦争の原因や責任は全て日本にある」としてきた東京裁判史観の下では、歴史の再検証による自己確認というものは許されないままできた。では、日本が企図した「大東亜戦争」は本当に潰えたのであろうか。戦場となった旧植民地はすべて戦中から戦後に独立を遂げ、再び白人国家の手に落ちたものはなかったという事実を、どう捉えるべきなのであろうか。昭和18(1943)年の「大東亜共同宣言」は、「大東亜を米英の桎梏より解放してその自存自衛を全うし」と謳い、また実際に戦場に赴いた兵士の手記でも、「アジア解放の戦いと思って戦っていた」という記述が多い。一方、我々はこれを、「あの忌まわしい戦争の偶然の副産物」と習ってきた。アジアの解放と大東亜戦争との間には、因果関係を見出してはならないと教わってきたのである。
しかし、ただ一度の戦争に負けたからとして、その戦争で自らが掲げていた理想の旗まで降ろして、自分たちの成し遂げたことに目を瞑ってしまってよいのであろうか。
「戦後レジームからの脱却」というテーマが未だに掲げられる時代に、新しいレジームを作り上げていくべき我々の背後の歴史には「無」があると思い込んでいては、日本人としての誇りの回復など到底覚束ない。
我々は一体何なのか、日本人であるということはどういうことなのか。この素朴な疑問に答えるためにも、もう一度「あの戦争」を虚心に振り返らなければならないと思うのである。先人の願いを無にしたままでいてはならない。