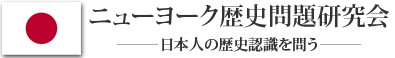歴史力を磨く 第32回
NY歴史問題研究会会長 髙崎 康裕
■ 日本人の宗教と道徳と愛国心 ■
以前のコラムで、「日本では道徳は教えられるものではなく、身につけているべきものであった」と書いた。その後読者の方から、では日本人の道徳観と宗教とはどのようにつながっているのかとの質問を受けた。
日本人の道徳観については、16世紀以降日本を訪れた西洋人が一様に驚き、そして称賛しているが、それは近代以降も変わっていない。大正10~昭和2(1921〜27)まで駐日フランス大使として日本に駐在したポール・クローデルに、『朝日の中の黒い鳥』という日本を考察したエッセイ集がある。その中でクローデルは、日本には何か永遠性があり、そこに日本の宗教があると書いている。「宗教の目的はすべて永遠なるものとの対比の下に、精神を謙遜と沈黙の態度の中に置くことにある」との定義を示して、宗教がないとされる日本人の日常の中にも宗教があるとした。同時に、「この国に生える大木が言葉では言い尽くせないようなゆっくりとした感覚によって、われわれが悪へ走ることへの拒否(ノン)を言う」との興味深い指摘もしている。
しかし、日本の宗教というものは上述の定義には適うものの、教義があり指導者がいるというような西洋の宗教の形にはなっていない。では、西洋的な宗教がなくとも、謙遜や沈黙の態度を保てるのは何故かとクローデルは問うた。そして、「日本人が自然の木や花や石の語る言葉の中に、永遠の智恵を聞き取る感覚を持っている。それが即ち日本人にとっての宗教的啓示なのだ」と読み解いた。即ち、自然が日本人の道徳を作り上げ、それが宗教にもなっていることを理解したのである。同時に彼は、日本人には自然の様々な存在、例えば大きな樹木を見るとそれがそのまま道徳の教えと映り、木に対しても道徳を見ているということに気づいたのである。大木というものが、言い尽くせない永遠の姿を以て、人間が悪に走ることに否を言うというような観察はまさに慧眼と言う外はない。
何か特定の超越的存在、つまり神への崇拝あるいは畏敬の念が道徳感に反映するとする西洋の考え方に対し、日本では自然と国土そのものが畏敬の対象であり、自然に対して頭を垂れる慎みの深さの背景にこそ、宗教や道徳があるというのが、日本人が長く無意識に抱いてきた感覚であろう。「日本人は、自分と国土との一体感を感じ取り、国土が自分たちに示す姿を前にして、深く敬虔な思いを抱いている。それが日本人の愛国心の根源の姿なのだ」というクローデルの言葉は、今の私達が忘れかけているかもしれない、世界から称賛された日本人の姿とは何かを語りかけてくる。