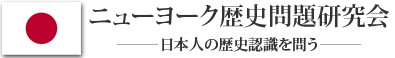歴史力を磨く 第31回
NY歴史問題研究会会長 髙崎 康裕
■ 第二の敗戦 ■
昭和20年9月2日に、日本国政府は東京湾内に侵入してきた米戦艦ミズーリ号艦上で、米国を代表とする連合国9カ国代表との停戦協定に調印した。しかし、この日に調印されたのは戦闘行為停止の協定であって、戦争の終結は日本対連合国間の平和条約が国際法上の効力を発現した昭和27年4月28日であった。その日までの約6年8ヵ月間は、軍事占領という形で、法的には戦争は継続していたのである。
そして、戦闘状態の終息と共に開始されたのが、勝利者側の連合国による今次大戦の自己正当化を図る情報宣伝戦であった。日本はこの情報宣伝及び心理戦においても悲惨な敗北を喫してきた。その象徴が現行日本国憲法であろう。
「日本国憲法」は、国家が敗戦の結果として国家主権を一時停止され、連合国軍総司令部の従属下にあった時期に、占領軍総司令部の下僚たちが6日6晩の突貫作業で作り上げた英文の原案を、急遽翻訳したものに過ぎないという事実は、今は誰もが知っている。それでありながら当時の「占領政策基本方針」に基づくその「日本国憲法」を、公布から70年間、その条文の一字一句も改定できぬままに我々はきてしまった。この憲法の桎梏だけでなく、我が国が米軍による占領期に受けた文化破壊の悲劇は、法制や社会構造、教育、宗教、そして広く精神伝統全般の分野に及び、そしてその破壊の傷痕は、講和条約の発効(国家主権の法的回復)を経ても完治することなく今日に至っている。
その背景には何があったのであろうか。そこには肇国以来初めて対外戦争に敗れたという挫折感や、全面的武装解除に応じてしまったことから来る無力感もあったであろう。しかし、日本国政府は降伏要求に応じたけれども、軍は未だ敗北していないし、中国大陸に展開している百万の陸軍はなお健在なのだという意識は、一部には確かに残っていたのである。降伏という形で停戦協定に調印した以上、敗戦を認めるのは仕方がないが、それでも正義を枉げない堂々とした敗者の姿を示すという考え方もあった。
しかし戦後の日本社会にみられたのは、国民啓蒙の意識に燃えた、マスコミや知識人と称される人々が口にする、戦争に対する反省・悔恨・呪詛の氾濫であった。同時に彼らがその言辞を弄するときの道徳的優越の表情や、祖国の歴史に対する批判的言辞を弄(もてあそ)ぶことで、己の優越性を手にし得るかのような態度であった。それらの言説をみる時に思い浮かぶのは、仕組まれたた近代主義という病弊に侵された知性の怠慢と、対日情報心理作戦がいかに日本の知識人社会に根深い害毒を浸透させたかという、第二の敗戦の悲しき現実である。
敗戦の原因は文化の優劣には関係がない。日本が敗北したのは「敵国と戦った結果であり、敗戦の惨禍をもたらしたのはその敵である。敗戦は世界史にはありふれた悲運であり、それは道徳的に反省すべき事態ではない。この経験を将来に活かし再生のための教訓とするというような、反省があればそれで十分であった筈なのだ。
敗戦は決して亡国ではない。それを齎すのは、強者に阿ね国家の矜持を忘れた国民の意識である。